まずは戦略を練ろう
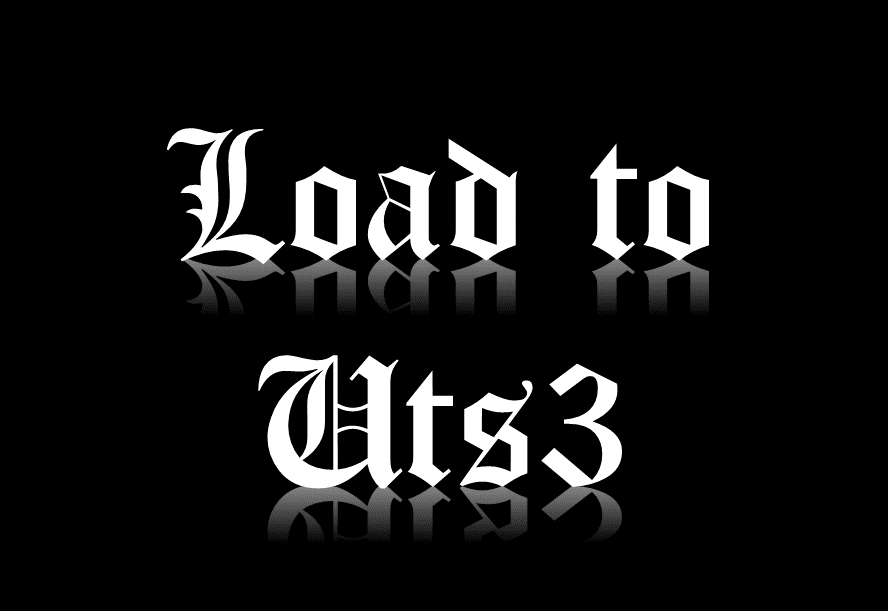
世間ではノウハウコレクターになるのは良くないと言われている。ノウハウコレクターとは、その名の通りノウハウばかり集めていて実際には行動しない人のことだ。でも、少なくとも勉強に限って言えば俺はこれが悪いことだとは思わない。ただし、期限を決めて情報を集める期間を設定しよう。
まず、敵をしることが大切だ。入試情報は東大や予備校のホームページから収集しておこう。これは、当たり前すぎるからここでは言及しない。
重要なのは、勉強を始める前に短期間で過去の先人の事例を(うまくいった人も惜しくも敗れたひとも)徹底的にそれもできるだけ沢山のサンプルに対して研究してから勉強に入ったほうがイイと個人的には思う。
研究というと大げさだが、要はデータを集めるのだ、その人のコアな考え方・指向性から使用している参考書、模試の点数、本番の点数、1日で捌ける勉強量など全てを肌感覚として知っておこう。
勿論、勉強を始める時点の個々の学力や他の分野での成功体験からくる努力のポテンシャルそして金銭面の問題等、素地や環境は人によって異なるわけでそのまま自分に当てはめることはできないかもしれない。だけどこれから得られるものは計り知れない。
かくある俺自身も、社会人を8年やり30歳になる今年の3月に受験を決意しているから、理三合格者の6割を占めている鉄緑戦士(現役&鉄緑)とは良くも悪くも大きくその状況は異なっていたが、それにも拘らず彼らの発信している情報から得るものは物凄く大きいものだった。
ただ、ある程度(自由な時間にもよるが1日中研究したとしたら1W位が限度だろう。俺自身は大学受験は素人に等しかったので、働きながら3月中の1カ月間はその戦略を練りに練ってシュミレーションし、仕事帰りに本屋に行っては毎日のようにどの参考書で攻めるかを徹底的に考えていた。そしていくつかのよさそうな参考書を片っ端から購入して(全教科で50冊位試しに購入したが予備校に通うより安いでしょ)、休日に実際に解いてみて、実際に繰り返し解きこむ参考書の候補を絞った。)
当然、仕事の休み時間と家に帰ってからは東大理三関連の書籍やネットの情報を毎日のように研究していた。
ただこの研究期間は長くても1カ月で卒業しないとイケない(俺は石橋を叩いて壊すくらい慎重だったけど、もともと勉強慣れしている人であれば1週間位で良いのかもしれない)。この研究期間卒業の目安は、新しく入ってくる巷の情報が殆ど既視感のある内容で退屈だと思える頃だろう。俺自身はアホなFラン卒の自称天才だが、次第に理三に合格した人の恐ろしく洗練されたプロのアスリートのような勉強法以外は受け付けないくらいこの期間に勉強法について洗練された自負がある。
研究したら、実際に走り始めてみてその過程で修正していくことが重要だ。というかこのころ(4月)は、ノウハウ収集に飽きて、実際に集めたノウハウを実践したくて仕方なかった。休日は全て勉強していたと思う。
ノウハウ集めは受験の最後まで続くことになるだろう。ただそれらのうちの多くは実際に問題を解き過去問を解き模試を受ける過程で自身の体験から得られる得点に直結する戦術レベルのものであるはずだ。ある程度大きな方向性さえ間違えていない(逆に方向性を間違えているということは最初の研究が甘かったということ)という前提で話をすれば、100聞は一見に如かずという諺は誠に正しい。
それとライバルについて研究しておくことが重要だ。合格者の高校別の内訳や、のちに別記事で詳しく触れるが、東大理三合格者の6割強(代々木鉄緑だけで40人、関西鉄緑[灘・洛南・東大寺・西大和・神戸女学院…]で20人ほど)を占める鉄緑会についても良く研究しておこう。
ぶっちぎりのトップ層以外の理三平均点を下回ってもなんとか滑り込もうと(このブログを読んでいる人の多くは後者だろう)考えている人間のライバルはこちらに通う都内の名門中高一貫校や地方の秀才達である(灘は比較的理三の上位層多いから除いた)。因みに地方組の多くは英検1級を東大合格前に保持していることが多い(レベル高い)。
TwitterのBioにIMO金とかIPhO金とか書いてあるのは大抵筑駒か灘のトップ層だから気にしなくていい(いくら自称メルエムの俺がイキったところで、こいつらのレベルには今からじゃさすがに届かない)。
最後に重要なことを補足しておくと、言わずもがな自身で試行錯誤して実際に集中して長時間勉強することで始めて上で仕入れたノウハウが血となり肉となるものだ。多くの先人の肩にのり、自身が心の底から頑張ったといえる努力ができれば、その時点で我々は半ば成功者だし、今度は我々が自身の泥臭い試行錯誤から得たオリジナルのノウハウを後進の人間に提供できることだろう。